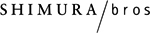
English
シムラブロスの“映画”の歴史
池上司
私がシムラブロスの作品を知ったのはそれほど昔ではない。わずかここ数年の話である。振 り返ると、2009 年の夏頃からグループ展などで見かけていたようだが、あまりはっきりとは覚 えていない。その後、2010 年の秋に京都で初めて彼らの個展を見たときの驚きについては後述 するが、なぜ、それまで、私は彼らの作品を見過ごしていたのだろうか。じつは、その些細な ことがらに、シムラブロスの創作を理解するきっかけが含まれていた。ともかく、経緯をひも といてみることにしよう。
実の姉弟であるユカとケンタロウは、2000 年頃にユニットとしての活動を始めている。ユカ がロンドンのセント・マーチンズに留学していたこともあり、当時の活動の舞台はヨーロッパ だった。それも、ベルリン国際映画祭タレント・キャンパス(2005)、ファム・フェスト(プラ ハ、2006)、カンヌ国際映画祭 SFC 部門(2007)など、当初はシアターを中心に作品を発表して いた。つまり、シムラブロスは若手の映像作家として活動していたわけだ。今ではむしろ、美 術館やギャラリーでの展覧会に参加することが多いシムラブロスだが、彼らの名を一躍高め、 かつ現代美術の分野でも注目されるきっかけとなったのが、初期の代表作《SEKILALA》 (2006-2008)である。 《SEKILALA》の素材は、彼らがプラハで撮影した 16mm 映画で、“高度な仮想現実技術で結 びついた家族の物語”を描いている。しかし、その内容はただ見ているだけでは分からない。 なぜなら、この映画は 3 面のスクリーンに、何かの物語というよりは近未来的世界観の断片を 示す 26 のシークエンスをそれぞれランダムに映し出すものだからだ。同じ組み合わせを目にす ることは確率的におそらくなく、始まりもなければ終わりもない。ここでは、通常の映画では 疑問視されない物語の単一性や連続性、すなわち編集という概念が解体され、観客の主体的な 想像力がそれをつなぐ不可欠の要素として構想されている。無論、すべてのシークエンスを通 して特定のテーマを暗示するという意味ではある種のモンタージュであるとも言えるのだが、 作品としての統一的な時間の流れを持たない点が大半の映像作品とは決定的に異なる。そして この構造自体が、“高度な仮想現実技術”がもたらすかもしれない主観的経験という“情報”の 等価性、交換可能性を表現するものであり、3 面のスクリーンに次々と投影される映像をまるで 3 人の家族の混乱した記憶のように見せている。 この作品を劇場映画として見るのはきわめて難しい。しかしながら、現代美術と考えると抵 抗なく受け入れられるのではないか。実際に、シムラブロスは 2009 年に文化庁メディア芸術祭 アート部門優秀賞を受賞し、《SEKILALA》は国立新美術館で上映される機会を得た。私が京都でこの作品を目にするのはそれからもう少し先のことだが、他の作品もこの受賞前後に現代美 術の展覧会に頻出するようになり、私も少しずつ彼らの作品に接していった。 しかしこの頃は、私はまだ、彼らがなぜそのような作品をつくっているのか想像がつかなか った。たとえば、ハイスピードカメラを用いてスラップスティック映画の身体動作を再現した 《EICON》(2008)、ディズニーのアニメーション映画のキャラクターを扱った《MMY: Mouse Made in Yokohama》(2009)などを知ってはいたが、現代美術の展覧会という枠組みのなかでは、 ハイテクなメディア・アートの一つにしか見えなかった。現代美術のフィールドには、スタジ オ・アッズーロや八谷和彦のように、インタラクティブなメディア・アートを手がける作家も 少なくない。したがって、シムラブロスの技術の高さに疑いはないものの、必ずしも技術的な 面で突出しているわけではない。また、シムラブロス以外にも、クリスチャン・マークレーや ミン・ウォンなどを筆頭に、既存の映画を素材として引用もしくは再構成することにより新た な映像表現を生み出す作家が、数多く存在することも事実だ。だが、シムラブロスの作品の特 長は、映画というメディウムの物質性と歴史性をより重視する点にある。 さて、私が見た京都での個展には《SEKILALA》の他に、同じく代表作である《X-RAY TRAIN》 (2008)と、当時最新作だった《FILM WITHOUT FILM》(2010)が出品されていた。《X-RAY TRAIN》は、実際には厚みのない映像というメディウムを立体的に提示しようとする試みだ。 今日の映画技術の生みの親であるリュミエール兄弟の《シオタ駅への列車の到着》(1897)をモ チーフに、機関車の CT スキャン画像を 12 枚の直列したスクリーンに投影することにより、迫 り来る光の量塊をあらゆる角度から鑑賞できるという未知の映像体験を生み出している。一方、 《FILM WITHOUT FILM》は、映画の基本文法であるモンタージュ理論を生み出したレフ・クレ ショフの“映画なしの映画”(1922)と題された実験を再現し、映画芸術の根幹とも言うべき光 の動きを 3 次元プリンターで物質化、視覚化している。とはいうものの、35mm フィルムのフレ ームサイズを基準とした親指ほどのオブジェクトは、見た目は彫刻に似ているが彫刻の概念で は語れない。いわゆる映像作品でもない。それまでの私のキュレーターとしての経験では、ど う位置づけたらよいのか見当がつかなかった。 コンセプトの強度は認めるものの、こうした作品ごとの手法のギャップになかば戸惑いなが ら奥の部屋までたどりつき、《SEKILALA》を 2 時間ほど眺めていると、ようやく彼らの目的に 思い至った。編集という概念の解体、映像の立体化、光の動きの物質化。これらの作品はいず れも、マルセル・デュシャンの“極薄”のような銀幕の彼方にある世界を、私たちの現実に開 こうとするものではないか。その都度手法は違うけれども、それが彼らにとっての映画史・映 像史に対する考察なのであり、結果的に映画でも研究論文でもなく、美術としか呼びようのな い形で結実したものなのではないか。そう考えると、作品としての様態が種々雑多なのも納得 がいく。“表現形式”はこの場合、問題ではないのだ。したがって、グループ展で一つの作品だ けを見ていても、個々の作品を貫く思想は分かりにくいものとなっている。それがおそらく、私が彼らの作品をかつて見過ごしていた理由である。 このように、新しい作品を目にするたびに狐につままれたような気分になるシムラブロスの 創作は、ヨーロッパのシアターを中心に活動していた頃から少しも変わらないのだろう。それ は美術とも映画とも名状しがたいものである。しかし彼らの取り組みは、決して既存の映画そ のものを否定しているわけではない。むしろかつての映画が持っていた、驚きに満ちた実験的 メディウムとしての物質性を現代に呼び戻そうとしているかのように感じられる。 このたびシンガポールで制作発表された《ROAD MOVIE – Road to Singapore》(2013)は、私 もスタッフの一人として企画段階から携わることができた作品だ。一見、色相と影がうつろう だけの抽象的な実験映画のようだが、私はある意味で痛快な娯楽作品に仕上がっていると思う。 彼らは NUS ミュージアムという会場を前提として、世界初のロードムービーであるビング・ク ロスビー主演の《Road to Singapore》(1940)をモチーフに、展覧会にともなう物の移動、人の移 動、さらには LKC ギャラリーに展示されているジョン・ミクシック博士の考古資料の由来を重 ね合わせて、サイト・スペシフィックなビデオ・インスタレーションを生み出した。この作品 は輸送中のクレートに落ちる光と影を撮影したものであり、映像を見ているうちに移動する主 体がクレートから観客自身にすり替わるような錯覚を与える。《X-RAY TRAIN》のように光を外 に引き出すのではなく、観客を銀幕の内側に引きずり込むような試みは、その前年に横浜で発 表された《SILVER SCREEN》(2012)と同様、シムラブロスの新たな方向性を示している。 シムラブロスの作品は、映画や美術といったジャンルの区別、あるいは美術館、博物館、国 際文化交流などの特定の文脈にこだわることなく、自由な精神と情熱をもって芸術に向き合う ことの重要性を私に教えてくれた。そしてこれからも、私は彼らが嬉々として語る映画の話に 耳を傾け、その作品を前に呆然としていたいと思う。シムラブロスの“映画”の歴史は、まだ 開かれたばかりである。*国立シンガポール大学出版カタログ「ROAD TO SINGAPORE」より
